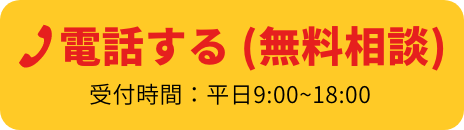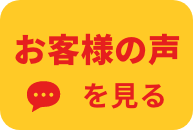消費税の仕組み

消費税の仕組み
会社経営をしていると必ず関わるのが「消費税」です。
和歌山県でも、中小企業や個人事業主のお客様から「消費税の計算方法が分かりにくい」「利益の10%を払うのではないのか?」といったご相談をよくいただきます。
実際、消費税はシンプルなようでいて誤解が多く、正しい仕組みを理解していないと経営判断に悪影響を与えてしまうことがあります。
ここでは、おりた税理士事務所(和歌山県和歌山市)を例に、分かりやすく解説していきます。
消費税は「預かった税金」と「支払った税金」の差額
例えば、売上が2,000万円(消費税込みで2,200万円)、仕入れが1,500万円(消費税込みで1,650万円)の会社を考えてみましょう。
「納める消費税はいくらですか?」と質問すると、多くのお客様が 2,000万円×10%=200万円 と答えます。ところが、これは間違いです。
消費税の本来の考え方は「預かった消費税と支払った消費税の差額を納める」というものです。
| 1. 預かった消費税(売上に含まれる消費税) | 2,000万円×10%=200万円 |
| 2. 支払った消費税(仕入れに含まれる消費税) | 1,500万円×10%=150万円 |
| 3. 差額(納める消費税) | 200万円-150万円=50万円 |
したがって、この会社が納める消費税は 50万円 となります。
「利益の10%を払うの?」という誤解
ここでよくある質問が、「結局、利益100万円に対して10%の10万円を払うのではないの?」というものです。
残念ながら、これも誤りです。
消費税は利益ではなく、あくまで 取引に含まれる消費税額のやりとり です。
利益が出ていなくても、売上に消費税を上乗せして取引をしていれば、その分の消費税を預かっているため納付義務が発生します。
たとえば赤字の会社でも、仕入れや経費にかかる消費税より売上に含まれる消費税が多ければ、納付が必要です。
逆に、仕入れや設備投資にかかる消費税の方が多ければ「消費税の還付」を受けられる場合もあります。
消費税の計算は複雑
和歌山県内の中小企業の経営者様からも、「消費税の納付額を誤って認識していた」「納税資金を用意できず資金繰りに苦労した」といった声を耳にします。
実際の計算はさらに複雑で、次のような要素も関係します。
-
・経費に含まれる消費税(交際費・通信費・外注費など)
・仕入税額控除の対象外となる支出
・簡易課税制度の選択(業種ごとにみなし仕入率を適用)
・免税事業者・インボイス制度への対応
特に2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書保存方式)によって、仕入先が免税事業者である場合には、その支払に含まれる消費税を仕入税額控除できなくなりました。
これにより、今まで以上に正確な処理が求められています。
和歌山県の経営者が注意すべきポイント
和歌山県の事業者様は、大都市圏と比べて取引先が地域に密着していることが多く、インボイス登録をしていない個人事業主や小規模事業者との取引も少なくありません。
そのため、仕入税額控除が制限され、思っていた以上に消費税の納付額が増えてしまうケースが出ています。
-
・仕入れ先にインボイス登録をお願いすべきか
・簡易課税制度を選択した方が有利か
・将来の納税資金をどう準備するか
おりた税理士事務所にご相談ください
おりた税理士事務所では、単なる申告書の作成だけでなく、経営に直結する消費税のアドバイスを行っています。
代表の織田税理士は、税理士業務に加えて実際に不動産賃貸業を営む経営者でもあるため、数字だけでなく経営現場を踏まえたサポートが可能です。
-
・消費税の正しい仕組みを知りたい
・納税資金を計画的に準備したい
・インボイス制度への対応を進めたい
そうしたお悩みをお持ちの和歌山県の経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ

消費税は「利益の10%」ではなく、「預かった消費税と支払った消費税の差額」を納める仕組みです。
単純そうに見えて、仕入税額控除やインボイス制度、簡易課税の有利不利など複雑な要素が絡みます。
おりた税理士事務所は、和歌山県で経営者様のパートナーとして、消費税を含む税務・会計・経営全般のご相談に対応しています。
誤解や不安をなくし、安心して本業に集中できるよう、織田税理士が全力でサポートいたします。
【事例:消費税の誤解と資金繰りトラブルを防ぐには】
事例①:赤字なのに消費税の納付が発生した製造業A社
和歌山市で部品加工業を営むA社は、年間売上8,000万円。2023年度は取引先の減少により赤字決算となりました。
社長は「赤字だから税金は発生しないだろう」と考えていましたが、実際には400万円の消費税納付が必要に。
売上に含まれる消費税:800万円、経費・仕入に含まれる消費税:400万円、差額=400万円(納付額)。
赤字でも「預かった消費税」が「支払った消費税」より多いため、納付義務が生じたのです。
A社では資金準備がなく資金ショートしかけましたが、おりた税理士事務所が資金繰り表作成と短期借入調整で延滞税を回避しました。
事例②:インボイス制度で納税額が想定以上に増えた建設業B社
海南市のB社(売上高2,500万円)は、免税事業者の大工との取引が多く、インボイス制度開始後も仕入税額控除できない経費が増加。
結果、納税額は想定より50万円以上増加し、予定していた機械設備更新を延期せざるを得ませんでした。
おりた税理士事務所は仕入先へのインボイス登録依頼をサポートし、簡易課税制度を比較検討。翌年度から簡易課税を適用し、納税額を安定化しました。
事例③:消費税還付で資金繰りが改善した観光業C社
白浜町の宿泊業C社は、1億円の設備投資(消費税1,000万円)を行い、初年度は売上200万円、預かった消費税200万円に対し支払った消費税1,000万円。
差額▲800万円が還付され、運転資金に充てることができました。これにより、従業員採用や広告投資も可能となり、開業後の成長を加速させました。
-
ポイント
・赤字でも消費税は発生する(A社)
・インボイス制度により仕入税額控除が制限される(B社)
・設備投資では消費税還付が資金調達手段になる(C社)