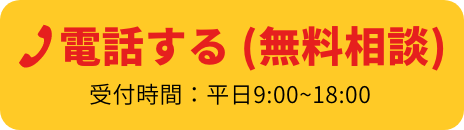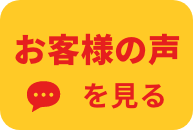節税対策(税金対策)

節税対策①(基礎編)~中小企業がまず取り組むべき税金対策~
知識編:節税の基本を理解する
節税とは、法律に基づいて税負担を軽減する正しい行為です。
一方で、架空経費の計上や売上除外といった違法行為は「脱税」にあたり、税務調査で発覚すれば多額の追徴課税とともに会社の信用を失うリスクがあります。
したがって、「正しい節税」と「危険な脱税」の線引きを明確に理解することが第一歩です。
特に中小企業における節税対策は、
・将来の資金繰りを安定させる
・経営者個人と会社のバランスを最適化する
ことが大きな目的となります。
知識編:代表的な基礎的節税対策
1. 役員報酬の適正化
法人における最も大きな経費が役員報酬です。
適切な役員報酬を設定することで、会社の利益を圧縮し法人税を抑えると同時に、経営者個人の所得税・住民税もコントロールできます。
特に、会社設立後初めての事業年度や大幅な利益増加が見込まれる年度は、「法人税」と「個人の税率」のバランスを意識した役員報酬の設計が欠かせません。
2. 生命保険を活用した節税
法人契約の生命保険は、掛金を損金算入できる商品も存在します。解約返戻金を活用すれば将来の資金準備にもなり、節税と資金繰り対策を両立できます。
ただし、税制改正により全額損金算入できる商品は減少しているため、税理士による精査が不可欠です。
3. 福利厚生制度の整備
役員や従業員に対する福利厚生費は、一定の条件を満たせば全額損金として認められます。
・慶弔見舞金
・健康診断費用
などは、従業員の満足度向上につながると同時に節税効果も得られる代表例です。
4. 少額減価償却資産の特例
30万円未満の資産については、年間300万円まで全額損金算入できる特例があります。通常は数年にわたり償却する資産も、即時に費用化できるため、黒字圧縮の効果が高い方法です。
5. 中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
年間最大240万円までの掛金が全額損金に算入でき、40か月以上積み立てれば解約時に全額戻る制度です。資金繰りリスクへの備えと節税効果を兼ね備えた制度として、多くの中小企業が活用しています。
事例編:和歌山の企業で実際にあった節税の工夫
事例1:建設業(和歌山市)
和歌山市内の建設会社では、決算時に利益が大きく出たため、役員報酬を適正化。結果、法人税の負担を軽減できただけでなく、経営者個人の所得税率も低い区分で抑えることができました。
👉 ポイント:「法人と個人の両面で最適化」することが、節税効果を最大化します。
事例2:製造業(海南市)
製造業を営む会社では、経営者の退職金準備のために法人契約の生命保険を活用。掛金を損金算入しながら資金を積み立て、退職時に解約返戻金を活用することで、税負担を抑えながら将来の備えを確保できました。
事例3:サービス業(和歌山市)
サービス業の企業では、従業員の定着率向上を目的に福利厚生制度を充実。社宅制度や健康診断費用の補助を整備することで、従業員の満足度が上がると同時に、福利厚生費として損金処理が可能になり、法人税の節税効果も得られました。
事例4:IT企業(和歌山)
和歌山市のIT企業が決算期に20万円のパソコンを10台購入(合計200万円)。少額減価償却資産の特例を活用し、購入年度に全額経費処理を行いました。結果、黒字を大幅に圧縮し、法人税負担を軽減することに成功しました。
事例5:金属加工業(和歌山市)
和歌山市の金属加工業では、売上の波動が大きいため、毎月20万円(年間240万円)を中小企業倒産防止共済に積み立て。掛金は全額損金算入され、当期の法人税が軽減。さらに、40か月以上積み立てれば解約時に全額戻るため、資金繰りリスクへの備えにもなりました。
まとめ

基礎編で紹介した節税策はいずれも「中小企業がまず取り組むべき王道の方法」です。
役員報酬の適正化、保険や共済制度の活用、福利厚生の整備、資産購入のタイミングなど、どれも経営の安定化につながる重要な施策です。
特に中小企業の場合、毎年の決算に合わせた小さな工夫の積み重ねが、将来の大きな差を生みます。
一方で、節税と脱税の境界を誤ると信用を失い、経営リスクを高めることになります。
必ず税理士など専門家と相談しながら、正しい節税策を選択していきましょう。
節税対策②(応用編)
1.知識編
応用編では、基礎編で触れた節税の基本的な仕組みをさらに発展させ、実際の企業経営に直結する応用的な節税策を整理します。
これらは中小企業や法人経営者が実務で直面しやすい論点であり、適切な知識と制度理解が不可欠です。
(1)役員と会社の資産取引の注意点
会社と役員個人との間で資産を売買する場合、必ず「時価」で行うことが必要です。
簿価や恣意的な金額で取引すると、
役員賞与扱いとなり、法人税・所得税の双方で課税される「二重課税」のリスクを負います。
(2)延滞税の負担
税金を遅延して納付すると「延滞税」が課されます。
延滞税率は金融機関の融資利率よりも高い水準に設定されており、
事実上「最も高い借金」となります。
資金繰りが厳しい場合でも、延滞を避けるため銀行借入を優先すべきです。
(3)棚卸資産の評価方法
期末の在庫評価は利益計算に大きく影響します。
評価方法や仕入れ時期によって、当期の課税所得が数十万円単位で変動することがあります。
適切な評価方法の選択・届出は節税の基本です。
(4)中小企業倒産防止共済
月額最大20万円を損金算入でき、資金繰りと節税の両立が可能な制度です。
40か月以上積立すれば解約時に全額戻るため、
「節税+リスクヘッジ」を同時に実現できます。
(5)少額減価償却資産の特例
取得価額30万円未満の資産は、即時に経費計上できます(年間300万円まで)。
IT機器や設備投資のタイミングによっては、
法人税を数十万円単位で抑制する効果があります。
(6)社会保険料の未払計上
決算月分の社会保険料は翌月払いとなるケースが多いため、未払計上を怠ると経費算入が漏れ、無駄に税負担が増加します。
決算時の基本処理として徹底が必要です。
(7)株式贈与による事業承継
自社株を少しずつ贈与することで、相続税の対象資産を分散・圧縮できます。
特に110万円の贈与税非課税枠を活用することで、
長期的に大きな節税効果が得られます。
(8)節税と脱税の違い
合法的な制度活用による節税は経営を守る「攻め」ですが、売上除外や架空経費計上といった脱税は重加算税や信用失墜を招き、
長期的に経営を危険にさらします。
2.事例編
① 製造業(和歌山市)
会社所有の土地(簿価500万円・時価1,000万円)を社長個人に400万円で売却。
見かけ上は100万円の損失だが、税務上は600万円が役員賞与扱いに。
法人税の課税所得が増え、社長個人にも所得税が課され、二重課税となった。
教訓:必ず「時価」での取引を徹底する。
② 建設業(和歌山)
法人税500万円を2か月以上遅延納付。延滞税率8.7%、6か月で約21万円の負担。
銀行融資であれば利率2%程度で済むため、延滞は割高。
教訓:延滞よりも銀行借入を優先する。
③ 小売業(年商2億円)
期末在庫100個、仕入単価が10,000円の場合は100万円評価、7,000円の場合は70万円評価。
30万円の差が課税所得に直結し、法人税額に大きな影響を与える。
教訓:在庫評価方法の選択とタイミング管理が重要。
④ 金属加工業(和歌山市)
月20万円を倒産防止共済に積立。年間240万円が全額損金となり、その年の法人税を軽減。
40か月以上積立後の解約で全額戻るため、資金繰りリスク対策にもなる。
教訓:「節税+資金繰り安定」を実現できる共済制度の活用。
⑤ IT企業(和歌山市)
決算期にパソコン10台(1台20万円)を購入。通常は4年償却だが、少額減価償却資産の特例で即時費用化。
結果200万円を全額経費処理でき、法人税約70万円削減。
教訓:特例を活用した設備投資のタイミング戦略。
⑥ サービス業(従業員15名)
3月決算で3月分社会保険料50万円を4月に支払う予定だったが、未払計上せず。
その結果、50万円分の経費計上が漏れ、法人税が増加。
教訓:小さな経費計上漏れが税負担に直結。決算処理を徹底する。
⑦ 老舗製造業(和歌山市)
社長(70歳)が後継者へ毎年110万円の自社株を贈与。10年で1,100万円分を移転。
相続発生時の株式評価額を圧縮し、相続税を軽減。
教訓:早めの贈与で事業承継の負担を分散。
⑧ 飲食業
売上の一部を除外し税務調査で発覚。重加算税35%と延滞税を課され、金融機関からの信用も失った。
一方で、共済や社宅制度の活用など合法的な節税策であれば、毎年100万円単位の負担軽減が可能。
教訓:節税は「攻め」、脱税は「自滅」。必ず合法的な方法で。
3.まとめ
応用編で取り上げた節税策は、いずれも「数字の知識+制度理解」が必要なものです。
特に和歌山の中小企業経営者にとっては、資産取引の適正処理、延滞税の回避、在庫や減価償却の正確な処理、
共済制度の活用、そして事業承継の早期対策が重要です。
ポイント整理:
・税金の延滞は絶対に避ける
・在庫評価や設備投資の特例活用は大きな節税効果
・共済制度は「節税+資金繰り安定」に有効
・事業承継は早めの贈与で負担を軽減
・脱税は信用失墜につながるため厳禁
節税はあくまで「経営を守るための戦略」であり、ルールを逸脱すればリスクが拡大します。
おりた税理士事務所では、和歌山県内の事業者様に対し、節税と資金繰り改善、事業承継支援までトータルでサポートしています。