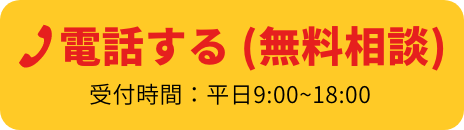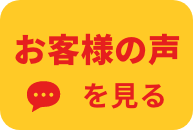役員報酬をしっかりと受取る

役員報酬をしっかりと受取る|和歌山県の中小企業支援ならおりた税理士事務所へ
会社経営において、社長や役員がどのタイミングで役員報酬を受け取るかは極めて重要な判断となります。
特に創業間もない企業や、利益計上が安定していない中小企業では、役員報酬の設定一つ「社長個人の手取り額」「会社の法人税額」「将来の資金繰り」まで大きな影響を及ぼします。
和歌山県で数多くの企業をサポートしてきたおりた税理士事務所でも、このテーマは社長様から非常に多くご相談をいただきます。
本稿では、具体的なシミュレーションと実際の事例を交えて「翌期から役員報酬を支給する場合」と「当期から役員報酬を支給する場合」を比較し、
そのメリット・デメリット、さらには実務で注意すべき点を詳しく解説いたします。
翌期より役員報酬を支給した場合の影響
例えば、和歌山県内の製造業A社(創業3期目、売上高600万円)の事例を考えます。
当期は役員報酬をゼロにし、そのまま600万円を利益として計上すると、法人税等で約150万円が発生。
結果として会社に残る資金は450万円です。
翌期にこの450万円を役員報酬として支給すると、社長個人には450万円が支払われ、所得税・住民税合計は約33万円。
社長の手残りは417万円となります。
一見、法人に資金が残るため良い方法に見えますが、法人税150万円が発生している点に注意が必要です。
当期から役員報酬を支給した場合の影響
同じA社が当期から600万円の役員報酬を設定すると、役員報酬が経費となり法人利益はゼロ。
法人税もゼロとなり、社長個人に600万円が支払われます。
この場合、所得税・住民税合計は約52万円で、手残りは548万円。
翌期支給と比較して130万円以上手元資金が増える結果となりました。
和歌山県内では実際に、当期支給へ切り替えることで資金繰りが改善した事例が多く見られます。
おりた税理士事務所の織田税理士は「法人税と所得税を総合的に考えた報酬設計が重要」とアドバイスしています。
社長個人の税金の目安
・年収500万円:所得税約14万円、住民税約25万円
・年収700万円:所得税約32万円、住民税約38万円
これらの数値からも、適切な報酬設定が節税に直結することがわかります。
実務上の注意点
- 役員報酬は原則として事業年度開始時に決定。期中の変更は業績悪化等、限定的な事由のみ認められます。
- 社会保険料増加の影響。報酬額に応じて厚生年金・健康保険料が増える一方、将来的な年金額増加というメリットもあります。
- 金融機関の融資審査で役員報酬が重要視される。安定した役員報酬は信用力向上につながります。
和歌山県の経営者様へのメッセージ
和歌山県は製造業、観光業、サービス業など多様な産業があり、景気変動により業績が左右されやすい地域です。
そのため、役員報酬の設定は単なる節税策ではなく、中長期的な経営戦略として位置づけることが求められます。
おりた税理士事務所では、織田税理士が経営者様の状況を丁寧にヒアリングし、法人税・所得税・住民税・社会保険料を総合的に考慮した最適なプランを提案。
将来の事業承継やライフプランまで見据えたコンサルティングを行っています。
役員報酬に関する正しい知識と戦略的な設計は、和歌山県の中小企業経営者にとって事業の安定・成長に欠かせません。
ぜひ一度、おりた税理士事務所へご相談ください。