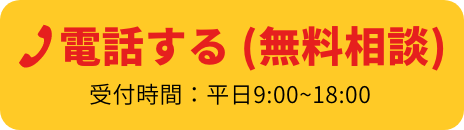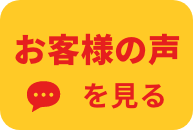配偶者控除・配偶者特別控除の改正と法人保険活用について

和歌山県で税務相談を多数受けている「おりた税理士事務所」では、所得税・住民税の負担に直結する配偶者控除・配偶者特別控除の改正について、多くのお客様からご質問をいただいております。
特に共働き世帯やパート勤務のご家庭にとっては、年収の調整次第で控除の有無が変わるため、毎年の年末調整や確定申告の時期に悩まれる方が少なくありません。
配偶者控除・配偶者特別控除とは?
配偶者控除とは、納税者(例えばご主人)に一定の収入以下の配偶者(例えば奥様)がいる場合に、納税者の所得税・住民税が軽減される制度です。
従来は「103万円の壁」と呼ばれており、配偶者の年収が103万円以下であれば、38万円の控除が認められていました。
一方、配偶者特別控除は、配偶者の年収が103万円を超えても一定の範囲内であれば段階的に控除が認められる制度です。
配偶者の働き方が多様化する中で、多くのご家庭に影響する制度といえます。
【具体例】
例えば、和歌山市在住のAさん夫婦の場合、奥様がパート収入110万円で働いていましたが、改正後は配偶者特別控除が適用され、Aさんの所得税が軽減されました。
これにより世帯全体の手取りが約5万円増え、年末調整で還付が受けられたケースがあります。
2018年からの改正ポイント
2018年1月以降の改正により、以下のような変更が行われました。
-
・納税者本人の年収制限が導入され、所得1,000万円超の場合は控除対象外。
・配偶者特別控除の対象範囲が「103万円超~141万円未満」から「103万円超~201万円以下」に拡大。
これにより、フルタイムに近いパート勤務の方や、和歌山県内でもサービス業や製造業で働く配偶者にとって有利になりました。
【具体例】
田辺市のBさんは、奥様の年収が180万円でしたが、改正後は一部控除が認められ、前年より約8万円の節税が実現しました。
控除を見込んで扶養範囲を調整した結果、社会保険の負担も考慮した最適な働き方を選択できました。
社会保険との関係
税金面の控除だけでなく、社会保険の被扶養者判定も重要です。
例えば協会けんぽでは、配偶者の年収が130万円未満であれば、被扶養者として保険料負担が不要になるケースもあります。
ただし、勤務時間が正社員の4分の3以上となると加入義務が発生するため、税務と社会保険の両面でシミュレーションが必要です。
織田税理士からのアドバイス
和歌山県のお客様を多く支援してきた織田税理士としては、配偶者の働き方を決める際には手取り最大化を意識することが重要です。
年収を数万円調整するだけで控除の有無が変わり、可処分所得に大きな影響を与えることがあります。
早めの相談で最適なプランを立てましょう。
法人保険に加入するメリット
和歌山県で会社を経営する方から多く寄せられる相談に「法人保険」があります。
おりた税理士事務所でも節税・資金繰りの観点でアドバイスしています。
法人保険とは?
法人が契約者となり、経営者を被保険者とする保険で、保険料が経費となる場合があります。
節税効果と具体例
掛け捨て型は全額経費、解約返戻金のあるタイプは資産計上されますが退職金の原資として活用可能です。
例えば和歌山市の製造業C社では、法人保険を活用し、5年後の社長退職時に退職金の一部をまかない、約500万円の税負担軽減を実現しました。
織田税理士のアドバイス
法人保険は商品ごとに扱いが異なり、安易な契約はリスクです。
必ず税理士に相談し、長期的な事業計画と整合性を取ることが必要です。
まとめ

配偶者控除や法人保険は正しい理解が重要です。
和歌山県で税務・経営相談をお考えの方は、おりた税理士事務所へ。
織田税理士が実例を交えて、節税・資産形成まで最適なアドバイスを提供します。